 ガイドラインについて
ガイドラインについて
データ復旧サービスのトラブルをできるだけ防ぎ、業界の健全化を図るため、ガイドラインを公表しております。
当協会が提唱するガイドラインは同業者の意見等を広く公募して多数意見を踏まえたガイドラインです。
このガイドラインはデータ復旧サービス市場全体に本ガイドラインの趣旨を広めることを目的としています。
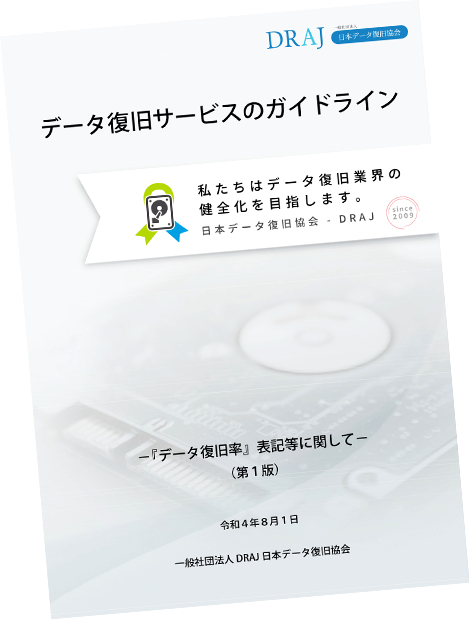
データ復旧サービスの
ガイドライン公開中
80%や90%などといった高いデータ復旧率の広告や宣伝をしていても
実際には全く異なる作業結果になりトラブルが起きることがあります。
そういったトラブルをできるだけ防ぐためのガイドラインとして公開しております。
データ復旧サービスの広告・宣伝によくある
「データ復旧率」表記が招きやすい被害
「データ復旧率」との宣伝文句を見てデータ復旧できると信じて当該宣伝の事業者に復旧を依頼してみたものの、
お客様側にとって納得できない作業結果となり、それにもかかわらず高い費用を請求される被害が見受けられます。


 ベンダー選定チェックシートについて
ベンダー選定チェックシートについて
このチェックシートは、マルウェア等に感染した端末や削除されたデータの復旧を、データ復旧事業者に依頼する際のトラブルを未然に防ぐためにご活用ください。
データ復旧事業者に復旧作業を依頼する組織の担当者が、復旧事業者が提示する「復旧率」「復元率」などの表記の解釈をめぐってトラブルに陥るケースが増えています。
トラブルのうちのいくつかは、組織の担当者の知識不足というよりも、事業者側が合理的な根拠のないまま、高いデータ復旧率を提示して広告宣伝を行っていることや、その復旧率について、サービスを利用する担当者に分かりやすい説明を行わないまま契約を締結し、利用者の想定する結果が得られないといったことに起因します。

「データ被害時のベンダー選定チェックシートVer1.0」は
以下の団体の合同編集で制作いたしました。
- 一般社団法人日本データ復旧協会(DRAJ)
- 特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)
- 一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)
- 特定非営利活動法人デジタル・フォレンジック研究会(IDF)
- 一般社団法人日本コンピュータセキュリティインシデント対応チーム協議会(NCA)

